とてつもなくお久しぶりな気がしています、けろです。
どうやら世間では2024年に突入してから半年以上が経過しているようで、そしてどうやら最後に記事を書いてからは1年が経過しているらしいです。怖。
久しぶりに何か書きたいな〜と思っていたところ、ちょうど渋谷のルミネで開催されていた呪術廻戦の原画展、「呪術廻戦展」に足を運んできたので、自分自身の備忘録も兼ねてダバダバ〜っと感想を書き連ねていこうと思います。
展示内容に関する具体的な言及は極力避けるようにしますが、それでも「こういうところが良かった〜」的な話はガンガンしていくので、完全初見で呪術廻戦展に臨みたい方はブラウザバック推奨です。
それではやっていきましょう、呪術廻戦原画展回です。
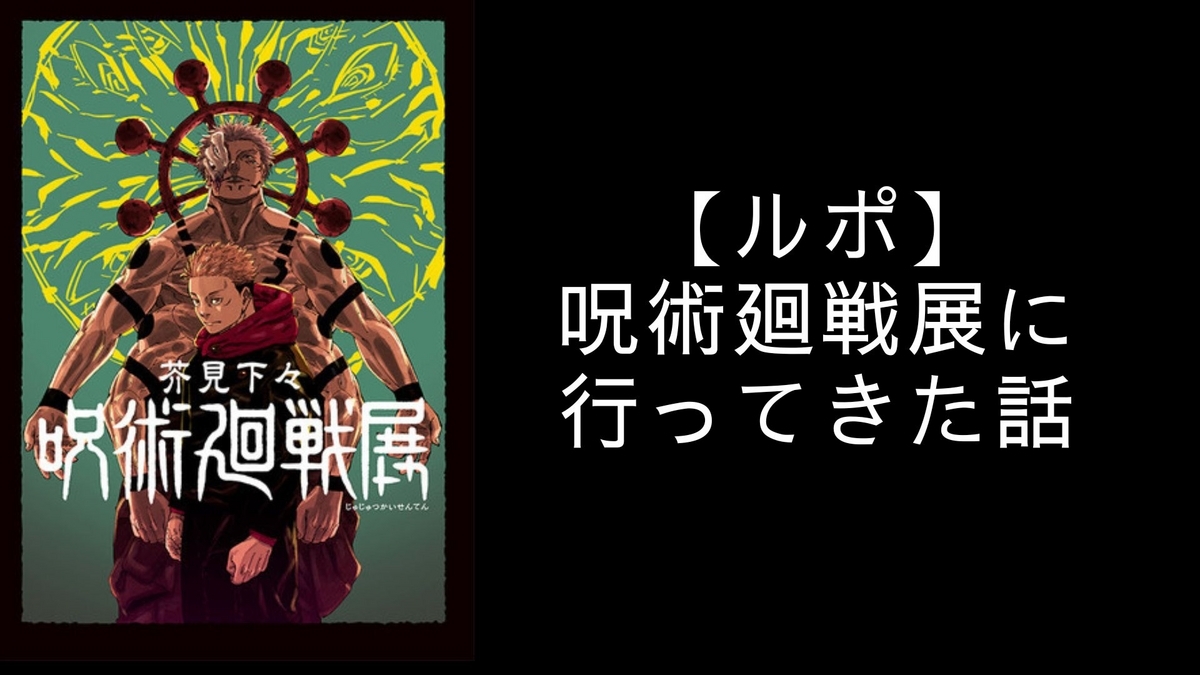
1.ここからは呪術廻戦展です
1-1.『呪術匝戦』との出会い
会場に足を踏み入れると、壁一面に見たことのない(しかし見覚えのある)漫画のネームが展示されていました。
作品のタイトルは『呪術匝戦』。そう、連載会議で"ボツ"を食らった『呪術廻戦』のプロトタイプのネームです。
僕はてっきり『東京都立呪術高等専門学校(以降「0巻」)』の後にすぐ『呪術廻戦』の形で連載になったとばかり思っていたので、『呪術匝戦』という作品はまさに幻の一作と言えるかもしれません。
浅い知識で恐縮ですが、連載会議には作品冒頭の1〜3話までのネームを提出するのが常らしく、会場内にはそのうちの一部が展示されていました。
特に驚いたのはその設定とストーリー展開。
「虎杖悠仁」はほぼそのままの設定でしたが、「伏黒恵」は「鰐淵恵」という名前のキャラクターで、「呪霊」も「怪病(けびょう)」という別の名称が付けられていました。
しかも『呪術廻戦』とは異なり、『匝戦』で体内にバケモノを宿しているのは「鰐淵恵(≒伏黒恵)」で、この頃から伏黒ポジションのキャラクターが受肉するのは決まっていたのか〜〜〜と感心しながらゾッとしていました。人の心。
あとはそうですね、物語開始早々に「死滅回遊(確か「回游」の字ではなかった記憶)」が始まり、術師同士の殺し合いを中心に話が展開し、「鹿紫雲一」のモデルになったと思われる「紫禁」というキャラクター(キャラデザはほぼ鹿紫雲)が出たり、ブラック企業で精神をやられたナナミンが呪詛師ポジションで登場したりと、『呪術廻戦』の下地にはなっているものの要所要所で今の作品の形とは異なっているのが面白かったです。
この手の「プロトタイプ」のネームを間近で見られる機会というのもそうそうないものだと思っているので、これを見られただけでも呪術廻戦展にきて良かったなと心から思いましたし、漫画家ってこんな風に我々の目に触れないところで途方もないほどの試行錯誤を繰り返しているんだな……と感銘を受けました。
展示されていた内容については公式図録にも掲載されていたものの全容は明かされていないので、連載完結後に『匝戦』の完全版ネームもどこかに収録してくれ〜〜頼むよ〜〜〜(傲慢)
1-2.Q&Aから滲む芥見先生の"理論派"な一面
この原画展、「原画展」と言われてはいるものの、芥見先生はデジタル作画で執筆されているので厳密な意味で「原画」があるわけではありません。
その代わりに「ネーム」「下書き」「背景」「キャラクター」等がレイヤーごとにデーターとして残っており、それらを展示することで"『呪術廻戦』という作品の制作過程を知ってもらう"というのがコンセプトになっています。
その中では芥見先生へのQ&Aがいくつもあって、「この展開はどの程度練られていたんでしょうか?」とか「このキャラクターとこのキャラクターの因縁について聞かせてください」みたいな感じで、芥見先生が『呪術廻戦』という作品を描く上でどのようなことを考えて執筆されていたのかが詳らかになっています。
あくまで個人的な感想になるんですが、芥見先生は多分ものすごく理論派で漫画を描いてるな〜〜と感じました。もちろん週刊連載を駆け抜けていく中で"ライブ感"で描くこともある(と言及がありました)と思いますが、根底には「漫画はこう描いたらいいんじゃないか」「こういうことすると読者に飽きられてしまう」「こういうのを大事にするといい」みたいな、漫画という創作物に対する一貫した価値観・哲学のようなものがある気がしています。
Q&Aの中では『BLEACH』や『NARUTO』といった有名ジャンプ作品以外にも『金色のガッシュ!!』や『Fate/Zero』みたいな作品も登場していて、いろんな作品を読み込んだ上でその作品の強みや魅力を理論的に分解しつつ自身の作品に取り入れてるな〜〜〜と感じました。
あるQ&Aでは『呪術廻戦』が完結した後のことについてもちょろっと触れていて、この作者なら一発屋で終わることなくどんどん面白い作品を生み出してくれるだろうな〜〜と(何様)。
1-3.ネーム→清書までの変遷を辿れる
この原画展で一番「ムホホホホホwww」とキショい声を出しそうになったのが、ネーム〜清書までの変遷を肌で感じ取れることです。
ネームはコマ割りと台詞を書き殴っているものが多かったんですが、ネーム→下書き→清書でキャラクターの台詞やコマ割りの構図が変化しているものがあってめちゃくちゃテンション上がりました。具体的なネタバレは現時点では控えますが、0巻のある台詞とか。
BLEACHの原画展の時にも書いた気がしますが、普段我々読者が目にできるのは「雑誌掲載」「単行本」という、商品として"完成"された形しかないので、こういった形で制作過程に触れられるのは、まさしく作者が血肉と魂を削って作品を生み出しているんだな……という感動を得られます。
kero-entame-channel.hatenablog.com
1-4.綿密な取材と下調べ
はえ〜〜となったのは渋谷事変や死滅回游に向けて相当な下調べとロケハンを行っていたところですね。
渋谷事変では時系列や場所がどんどん変わっていくので、物語としての整合性が破綻しないように気を遣われていたようですし、死滅回游の日車の回想については弁護士の方に添削をいただく等、物語にリアリティを持たせるようめちゃくちゃ苦心されていた点ですね。
個人的には日車に関するエピソードでの弁護士の方とのやりとりがかなり好きです。法律面や法曹界隈特有のあるあるなんかを的確にお伝えされていて、それを元に死滅回游のあのエピソードが出来上がったんだな、と。ちなみに芥見先生はその弁護士の方を「編集の才能がある」と絶賛していました。
ロケハンができない時もGoogle Mapでその場所の光景を参照する等、多分創作に携わる人であれば多くの人がやっていることではあるんだろうけど、それでも一般人目線だと制作側の労力や"人間味"のようなものを感じられて、貴重な経験でした。
2.今はただ、アシスタントにも感謝を
2-1.今の漫画制作現場ってすごい
先にも触れた通り、『呪術廻戦』はデジタル作画の制作体制をとっていて、下書きや背景がレイヤー別のデータとして残っています。
この原画展でもそれらが展示されていたんですが、めちゃくちゃ驚いたのはその制作体制。
自分の中で「漫画執筆」というと『バクマン。』で描かれていた仕事内容のイメージが色濃く、作者がキャラクターを描き、その後アシスタントの方々が背景を描くといった進め方が「漫画執筆」だと思っていました。
ところが『呪術廻戦』では完全分業というか、芥見先生がネームを元に背景やモブキャラに関する指示を出し、アシスタントの方々がそれを元に自分のタスクを独自で進めるという体制で、「原作者がキャラを仕上げるのを待つ」という工程が発生しない形になっていました。
これって多分デジタルでの制作ができるようになってから広まったのかな?とも思っているんですが、芥見先生がキャラを描き、アシスタントの方が描いた背景をレイヤー処理で重ねて仕上げていく制作工程はシンプルに全く知らない世界だったので感動しました。
しかも芥見先生自身は複数話の構成を同時進行で考えているらしく、先の話のネームを書きながら直近の話のペン入れ、みたいなことをしているようで、自分だったら進捗管理できずに死を迎えそうだなと感じました。
というか連載されてる作家の方々はみんなこんなことしてるんですか?週刊連載ってもしかしなくても通常の人間がこなせる所業ではない???
2-2.芥見先生の雑な指示出しがおもろい
ちょっとだけ原画展の内容に触れちゃうのでお気をつけを。
芥見先生自身が「最悪の指示」と評しているものがあって、九十九由基が登場した時のバイクについての指示出しで一言「ハーレー」とだけ書いてあったのが最高に雑な指示出しで笑いました。
そんでその指示を元にかっちょいいバイクを描き上げてるアシさんもすげぇな、と。
こういうのって作家とアシスタント間での信頼関係がないとできないことだと思うので、芥見先生の職場環境もきっと面白いんだろうなと勝手に想像しています(原画展での言及から察するにコロナ禍以降はリモートなのかな?とも思いますが)。
3-3.アシスタント陣への感謝が伝わってくる
「漫画の原画展」の中では異色?かもしれないんですが、各アシスタントさんのお名前を取り上げた上でその方がどんな方でどんな作画が得意なのか、どんな時に助かったのかみたいなことをかなり細かく言及していて、アシスタントさんの名前と担当された背景の原画がフォトスポットとして展示されていました。
(ひっそりとした展示ではなく、かなりしっかりとした感じ)

こんな感じで、各アシスタントの方々のお名前と担当された背景をデッカく展示していて、この横にはそのアシスタントさんとのエピソードも交えながらかなり長文であれこれと語られていて、「漫画の原画展」というテイストの中でここまでしっかり制作現場を支えている方について言及するのも珍しいな〜〜となりました。
芥見先生自身も「アシスタントさん達の仕事を皆さんに紹介できたことが何より嬉しいです」と語っていたので、この原画展の目的の一つに"普段あまり語られることのないアシスタントのお仕事紹介"もあったんだろうな、と思いました。
これまで語ったことは全て「公式図録」に掲載されているので原画展に行かなくてもその全容に触れることはできるんですが、やっぱりデカい空間に展示されているネーム・原画の数々は圧巻ですし、こういうのは五感で体感してナンボだと思っているので、皆さんもぜひ原画展に足を運んでみてください。普段インドアの自分が言うんですから間違いありません(?)
久しぶりに文字を書いたと思ったら4000字も書いていたみたいです。今年はもう少しあれこれ書きたいですね。
それではまた。
よしなに。


